白馬五竜アルプス平にはAlps360というレストハウスがあります。
Alps360はゴンドラテレキャビン隣の建物で、白馬五竜高山植物園を散策する拠点として、五龍岳登山や小遠見山へのハイキングのスタート地点となります。
ゆっくり、天候に合わせ、風に合わせ、日の光に合わせ、音に合わせ、変わりゆく景色に合わせ。
アルプス平で本など読みつつ過ごす時間・・・。
撮影地:長野県北安曇郡白馬村 白馬五竜 アルプス平
撮影日:平成二十九年六月二十二日
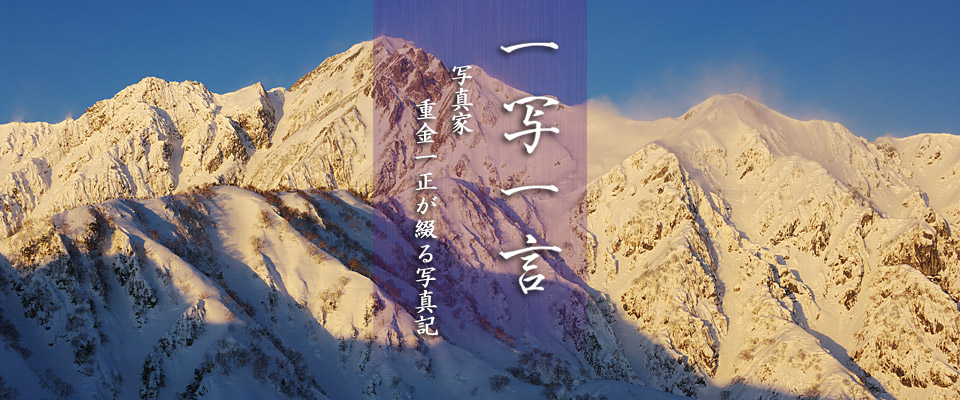
写真展の準備のため平成二十九年六月月二十二日から二十五日まで白馬五竜に滞在していました。
白馬五竜高山植物園で撮影した花です。
昼間は写真展の展示設営を行うため、撮影は朝、夕方で露出も上がらず、曇りがちで配光や環境に変化がないと、ただ撮っただけの写真になってしまいます。
コマクサはこれから見頃を迎えます。
シラネアオイはそろそろ終わりで、撮影した花も雄しべ雌しべに茶色く痛みがあります。
ミヤマオダマキは見頃で青紫の花がたくさん咲いていました。
他にもチングルマやミネズオウ、アオノツガザクラなどが見頃を迎えていました。
---
撮影地:長野県北安曇郡白馬村 白馬五竜 アルプス平
撮影日:平成二十九年六月二十三日、二十四日
---
平成二十八年九月十日から十三日まで写真展での最終のご案内と撤収作業に合わせ白馬五竜に滞在していました。
前もっての天候予報で天候は良くない事はわかっていましたが、もともと雨男ですから、諦めずに撮影準備はしていきます。
九月十一日、日没を迎えたアルプス平ではやはり雲だらけ。
ですが、時折見せる五竜岳の姿に撮影機会が得られることを祈りつつ・・・
太陽は雲の周りにできる彩雲、雲によって乱れた荒々しい「光環」を伴って降りてゆきました。
雲の形状から環のようにはなっていないのですが、一様の薄い雲ならば綺麗な輪になっていたかもしれませんね。
五竜岳G0峰あたりに沈んだ太陽の光は、大黒岳の周囲から光が漏れて水平に近い光線を放っていました。
光の向きによって薄明光線、その反対を反薄明光線と呼びますが、水平の場合はどちらになるのだろうか???
撮影地:遠見尾根、アルプス平(長野県北安曇郡白馬村神城)
撮影日:平成二十八年九月十一日
八月九日から十五日まで白馬五竜に滞在しておりました。
ちょうどペルセウス座流星群の時期でありまして、五竜岳と流星との共演を捉えるべく…。
※写真はクリック、またはタップすると大きく表示できます。
五竜岳と流星

よく見ると、流星に色があり、緑色からオレンジ色に変化しているのがわかります。
流星は地球の大気圏突入時に燃える色でその成分がわかるようで、緑色は「鉄」、オレンジ色は「ナトリウム」らしいです。
はっきり色がわかるように写ったのは私は初めてかもしれません。
白馬村の夜景と流星

流れ星は、画面右上、星がグチャっと固まっているプレアデス星団(和名:昴)から少しだけ左上にシュッ!っと写っています。
中央より少し左上の一番明るい星はぎょしゃ座のカペラです。
撮影地:長野県北安曇郡白馬村 アルプス平
撮影日:平成二十八年八月十一日
平成二十五年十月、膝の手術をする事が決まったあと、入院前に松葉杖をつきながら長野県小布施町に滞在静養しました。その時に小布施町立図書館に行きまして、信濃毎日新聞社が昭和五十八年発刊の『信州山岳百科』という本に出会いました。
五竜岳の名前の由来や歴史が書かれているのですが、今まで読んだ本の中で一番妥当だと思える内容だと思い、コピーを取らせていただこうと司書さんにお聞きしたら、残念ながらこの本はコピー不可に指定されていました。
どうにかしたいと思いまして、『信州山岳百科』の五竜岳、遠見尾根に関する部分を、6時間かけて、持っていたノートに全部書き写したのです。
時は流れ・・・
五竜岳のことだけならば、書き写したノートがあれば済むのですが、この本の内容で周辺の山のことも知りたいと思うと、手元に必要と感じるわけで・・・
最近、その『信州山岳百科』を古本で購入しました!
すでに絶版本で、『日本の古本屋』でもなかなかの価格ですが、運良く格安で入手することができたのです。
五竜岳の名前の由来については、また別の機会に改めて書いてみたいと思います。
平成二十八年六月二日