羽織紐のとんぼ玉を、所沢市在住のとんぼ玉作家、清水さんに作って頂きました。
元は、小さい紺色のとんぼ玉だけだったのですが、紐の色に対してあまりに暗く地味…。
なにか主役となるべきものが欲しい…
というわけで、明るい色で大きめの青海波柄のとんぼ玉を作って頂きました。
※写真画像はクリックまたはタップすると大きく表示できます。
青海波柄の角帯があるので、とんぼ玉の柄も青海波に合わせてみました。
かなり気に入ってます😊
埼玉県所沢市のとんぼ玉作家「敬とんぼ」清水さんのぶろぐへリンク
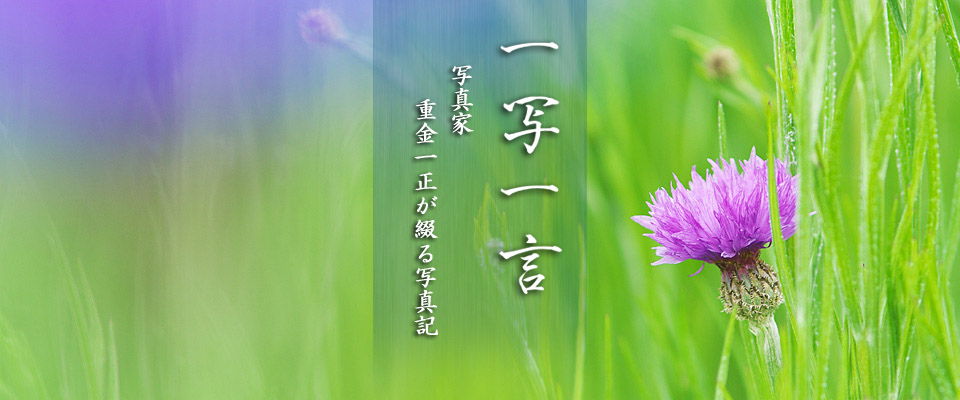
羽織紐のとんぼ玉を、所沢市在住のとんぼ玉作家、清水さんに作って頂きました。
元は、小さい紺色のとんぼ玉だけだったのですが、紐の色に対してあまりに暗く地味…。
なにか主役となるべきものが欲しい…
というわけで、明るい色で大きめの青海波柄のとんぼ玉を作って頂きました。
※写真画像はクリックまたはタップすると大きく表示できます。
青海波柄の角帯があるので、とんぼ玉の柄も青海波に合わせてみました。
かなり気に入ってます😊
埼玉県所沢市のとんぼ玉作家「敬とんぼ」清水さんのぶろぐへリンク
平成三十年八月二十五日
伝統工芸 青山スクエア「企画展 和くらし大好き! 集まれ女匠衆 第2部」の上田紬、小岩井工房の小岩井カリナさんの展示を見に行ってきました。
小岩井カリナさんご本人も在廊されていまして、お話を聞くことができました。
写真に、ちゃんとご本人も入れて(顔は出ないようにして)写しています。どこに写っているかわかりますか~?
左側に気になっていたお召しのストール。
冬のマフラー代わりにと思いますが、さすがお召しです😅。
—–
男物の単衣の角帯。
気に入ったのが2本あったのですが、陰影をつけたような市松柄で立体感があります。
この色良いなぁ~…。
—–
女性ものの、八寸帯です。
離れて見て、近づいてゆくほどのに織り、柄の面白さ、色使いが見えてきますね。
写真もそうですが、色というのは無限な気がします。だから奥が深く楽しい。
人が幅広く明るさと色を認識できることは大変に幸せな事。
—–
小物がたくさんあります。
中には黄色と黒のハンチングと角帯と財布と・・・〇〇ファン着物で応援仕様😲
この引き出しを利用した展示、いいですね~。
棚の上からの視線移動もしやすいですし、個々の商品が引き立ちます。人によってはしゃがんで手に取られてゆっくり見ることにもなります。
とても展示方法の勉強になりました。
—–
男物の角帯を見せて頂こうと・・・。
小岩井カリナさんの手先二本が今回気に入った色柄の角帯。
在場されていた小岩井カリナさん、明るい涼しげな青に縞のお召し。とても素敵な御姿でした。
お会いする度、お話をお聞きするたび、ますます上田紬が好きになります。
—–
平成三十年八月二十五日
伝統工芸 青山スクエア「企画展 和くらし大好き! 集まれ女匠衆 第2部」にて
平成三十年六月五日、埼玉県所沢市北野南の養蚕農家へ行って参りました。
現在、所沢市の養蚕農家はここ一軒だけ。
ありがたいご縁で、見学させていただくことができました。
写真一)営繭(えいけん)の部屋
お蚕さまが取り付いた蔟がたくさん吊ってあります。
上に行きたがる習性をもつお蚕さま。
蔟を登って上へ上へ…。
写真二)
みんな上に上がるとバランスが崩れて吊ってある蔟がくるっと回ります。
下になってしまったお蚕さまは、また上へ上へ。。。
そうこうしてるうちに、適当な時に営繭がはじまり、いつのまにかバランスが取れているそうです。
写真三)営繭中の繭
写真四)出来上がった繭
営繭を始めてから10日程度で完成とのことです。
とても細い糸で綺麗な繭ですね~。
ここから糸を取り出すのかと思うと、どこが最初?
糸の始まりはどこなんだろう???
—–
撮影地:埼玉県所沢市北野南
撮影日:平成三十年六月五日
—–
平成三十年六月五日、埼玉県所沢市北野南の養蚕農家へ行って参りました。
現在、所沢市の養蚕農家はここ一軒だけ。
ありがたいご縁で、見せていただくことができました。
写真一)桑の葉をちょっとだけお食事中のお蚕さま
繭を作り始める直前で、すでにほとんど食べません。
写真二)桑の葉を食べて育つ部屋ですが、そろそろ食べ終わり。お蚕さまを集めて、繭を作る(営繭・えいけん)部屋に移動する準備をしていました。
写真三)集められたお蚕さま
写真四)営繭を始めます。
繭を作る(営繭・えいけん)部屋で、蔟(まぶし)と呼ばれる枠にお蚕さまを放します。
お蚕様は上へ登る習性があるそうで、その習性を利用して蔟(まぶし) と呼ばれる枠に登らせます。
写真五)蔟(まぶし)を登るお蚕さま
そういえば、なぜか上を向きたがっています。
イナバウアーが上手です!
つづく・・・
—–
撮影地:埼玉県所沢市北野南
撮影日:平成三十年六月五日
—–
平成三十年六月十六日
東京都新宿区、下落合(最寄り駅は目白)にある花想容さんといふ着物屋さんに行ってきました。
大正時代の日本家屋で営業されていて、緑豊かなお庭から飛び石を歩いてお店に入ります。
当初の予報は雨でしたが、傘を使わずに済みました。
お手入れのキャンペーン中ということで、多くのお客さんが来られていました。
また、ゆっくりと再訪したいと思います。
平成三十年五月十四日
伝統工芸 青山スクエアへ「上田紬 小岩井紬工房展」を見に行ってきました。
リンゴ染めの機織り体験ですが、写真は伝統工芸士の小岩井紬工房代表の小岩井さんの手さばき。
はやっ!これは持ってくる写真機を間違えた😅
まさか撮影可とは思ってなかったので、古いサブ機しか持ってきてなかったのです。
りんご染め🍎🍏花瓶敷の機織り体験用に張られた美しい経糸。
どんな仕掛けになってるのか観察...ん〜ん?
りんご染め。ふんわり柔らか。りんご色な空間。🍎🍏美しい。。。
なんと!りんごの種類によって色が違うらしい。
撞木(反物掛け)、左から「秋映」「シナノゴールド」「シナノスイート」
今日、なに食べる?いや、何着る?
今日はシナノスイートにしよう...なんて思ったり会話があったり???
はぁ~、美しい…
ため息が出てしまいます。
東京都港区、伝統工芸 青山スクエアで5月16日まで。
最寄り駅は青山一丁目駅です。
—–
撮影地:東京都港区 伝統工芸 青山スクエア
撮影日:平成三十年五月十四日
—–
平成三十年年二月二十五日
東京都新宿区 中井駅周辺で行われている「染の小道」に行ってきました。
前日に続き、連日で染の小道へ。
この日は、私も着物で…。
写真一)
昨年も楽しかった石橋湯のし店さん。
湯のし屋さんは激減していて貴重なお店です。
写真二)
石橋湯のし店さんでは着物の古着や新古品の反物、帯などが売られていまして、その色柄を見るのは楽しいです。
やはりここでも緑色の反物に目が反応してちょっと広げさせてもらいました。
なんと綺麗な緑色、絵柄にも程よく緑が使われてキレイ。
写真三)
二葉苑さんでは展示室に上がりまして、色鮮やかな反物をたくさん見てきました。
呉服店に行くというのは少々緊張しますが、着物を着た職員さんがとても感じ良く、気さくに説明してくださいました。
少々気になる反物がありまして、、、大胆な絵柄で格好よく一目ぼれ!
しかし、近づいて見ていないため生地が正絹だったか木綿だったのかわかりませんが、浴衣にしたらあれはかっこいい!
写真四)
前日(二月二十四日)は撮影目的の割合が多く写真機鞄を持つため洋服でしたが、翌二十五日は友人も遊びに来るということで、写真機は小さなものにして着物を着て行きました。
写真機材を入れる鞄は、生地が硬かったり金属やプラスチックが多用され、正絹の着物の生地を傷めやすいのです。
着物を着ても扱える鞄か、写真機鞄をガシガシ使える木綿の着物が欲しい・・・。
友人に、後ろ姿を撮って頂きました。
少々、羽織のたたみしわが気になりますが(^^;)
羽織程度で過ごせる陽気で良かったです。
今年も楽しい染の小道でした。
撮影地:東京都 新宿区中井駅周辺
撮影日:平成三十年二月二十五日
平成三十年年二月二十四日
東京都新宿区 中井駅周辺で行われている「染の小道」に行ってきました。
妙正寺川の反物展示をはじめ、周辺の店舗でのれんの展示、友禅染の工房見学や体験、着物の湯のし工房での見学や、着物に関する小物などの展示や販売などがあります。着物で来られている方がとても多いです。
写真一)風に舞う反物。
写真二)風があってブレやすい。。。ならばブラしてしまおうと、NDフィルターを付けてスローシャッターで撮影。
妙正寺川の水面も柔らかくなりました。
写真三)
染の小道が開催されている、中井の駅周辺では、運営関係者をはじめ観光で訪れている人も着物を着た方をたくさん見かけます。
やはり皆さんどんなのを着られているのか気になります。※奇抜やだらしない着方をしているのは除く
写真四)
次は女性のかた。。。
この方の着物はすれ違いざまに一目でいいなぁ~と思いつつ、やっぱり撮らせてもらおうと、振り返って追って、声をかけて撮影させていただきました。
つづく・・・
撮影地:東京都 新宿区中井駅周辺
撮影日:平成三十年二月二十四日
平成三十年一月七日と八日は、某写真館で成人式に合わせたスタジオ撮影を行いました。
中判フィルムとデジタルの両方で撮影で、私は主にデジタルを担当していましたが、一部中判のフィルムでも撮影。
デジタルは、後の画像処理の関係などのこともありスタジオの機材、富士フィルムのX-T2で撮影しました。
瞳認識AFで軽快に撮影できますが、ボタン類や画面の表示文字やマークが小さてわかりにくいです。
成人式の当日に撮影に来られる方は、男女ともにご家族揃い。
そして、女性の振袖は全員が母親からとの事でした。
新成人の方の祖父の代まで呉服店を営んでいたというご家族は、なんと偶然に以前近所に住んでいた方で驚きました。元呉服店だけに、さすがの京友禅の振袖と美しい帯で、スタジオに入ってきた瞬間に「うわ、すごい!」と。
男性は全員スーツでしたが、撮影時だけでもきちんとした日本人の第一礼装である黒紋付はいても良かった気がします。※金ぴかなバカ殿姿は除く。
夜、十時ごろ、駅近くで酔っ払ってワーワーギャーギャー騒ぎ、座り込んだりしている新成人を横目に帰りましたが、祝い事の裏でまさかあんなひどい事件が起こっていたとは。。。