夜桜とともに。
令和七年四月四日未明、自宅近くの公園にて。
写真用閃光(フラッシュ)三灯による配光で撮影。
雨上がりの湿度と夜露の影響で光が拡散し良い雰囲気の光になりました。
被写体となってくれる人はいないので、自分でやってます(^_^;)
着物、地毛で髷を結っています。
日本ブログ村に参加しています。
ぽちっと投票お願いします。
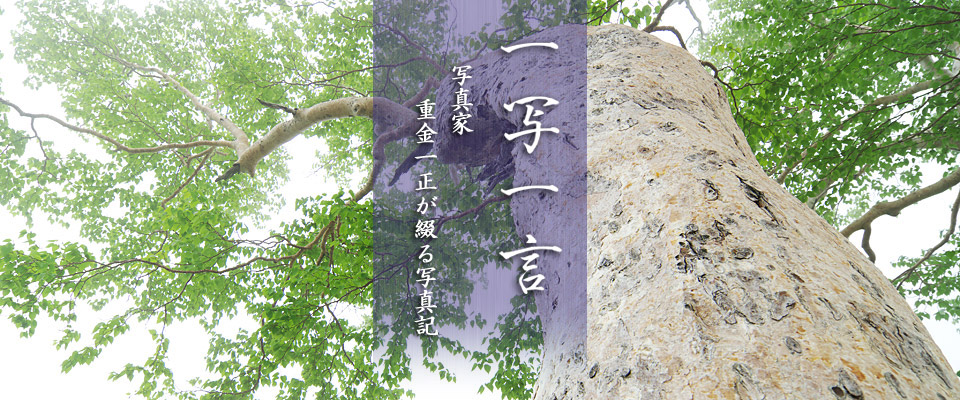
令和七年三月二十九日
武州川越の一番街で行われていた「江戸の日」、地毛髷の結髪実演、どんな雰囲気で行われているのか、見ておきたいと思いまして。ちょいと行ってきました。
見物者は三十人程度かと思いますが傘をさしての立ち見では それ以上の見物人数は難しいでしょう。
雨の中としては盛況だったのではないかと思います。
手伝っている写真館で 成人式の撮影時に日本髪風な方を撮影することがありますが、”日本髪風”ではなく本職の結髪師さんが本格的な日本髪を結うと その仕上がりと美しさに圧倒されます。
女性の髷は華やかで良いです。
が、写真を撮ることを忘れました(^_^;)
—
川越ですので私も髷を結っていきました。
見物者の中にSNSで相互フォローになっている「未告」さんがおられまして、私の写真を撮ってくださいました。
ありがとうございます。
私自身は一枚も写真を撮ってなかったので、撮っていただいた写真の中からの投稿です。(少し画像処理しています)
髷尻を後ろから見た時の🍙おにぎり型、私のこだわり部分です😊
日本ブログ村に参加しています。
ぽちっと投票お願いします。
令和七年三月二十六日
自宅で育てている「岳樺・だけかんば」に萌芽(ほうが)が出てきました。
私が一番好きな樹木で、大きく育つと人の肌のような樹皮をまとい、山の斜面にも力強く立ち、舞うような樹形と繊細な枝ぶりは美しく魅力を感じるのです。
岳樺は高山や寒冷地、森林限界上部に生育する落葉広葉樹の高木です。
標高が低く気温が高い我が家ではすでに萌芽が出てきました。
夏の最高気温が三十五度を超える当地でも育ちますが、寒冷紗をしたり鉢が日光で温まらないように断熱シートを巻いたりしています。
この岳樺は白馬五竜高山植物園で園内管理の都合上、間引きした幼木を譲っていただいたものです。
年にもよりますが、夏の白馬五竜エスカルプラザでの写真展会場で、私が滞在中にこの岳樺を展示することがあります。
しばしの里帰りです。
日本ブログ村に参加しています。
ぽちっと投票お願いします。
和裁士さんに仕立て依頼していた毛織の長着が仕上がってきました。
反幅の狭い(おそらく女性向け)反物なので裄に接ぎを入れていただいてます。
今回、江戸時代末期の写真などを参考にしつつ、衽の寸法を、現代の男物の一般的な仕立て寸法形式とは変えていただきました。
とはいえ、江戸時代末期の写真を測ったところでそんなに細かいことまではわからないわけで「何となくそう見える」程度からの想像をもとにしています。
通常より動きやすく裾さばきしやすくしています。
反物生地について...
あまり見たことがない細かい織模様が気に入って購入した反物でしたが、毛織にしては滑らかな風合いで、絹ほどではないですがさらっとするっと肌触りの良い生地。
軽くて薄手、少し透け感があります。
入手時のときにすでに証紙など織元を示すものがないのが残念。
この反物に準じた別の反物も見てみたかったです。
日本ブログ村に参加しています。
ぽちっと投票お願いします。
令和七年二月二十二日 東京都新宿区 西武新宿線中井駅周辺で行われている『染の小道』に行ってきました。
毎年、楽しみにしている催事です。
今年は男着物な友人四人(一人は今回洋服)で散歩(徘徊)。
楽しくて写真を撮るのを忘れて数枚しか撮ってませんでした。
—
写真一

東京手描友禅作家 飯島武文さんの作品を撮ろうとしたけど風で舞うため友人に押さえてもらったら…
作品の前で友人が見得を切ってる写真になりました。
—
写真二

染の里おちあいさんの展示室
催事がないと入れない展示室なのですが、お気に入りの場所。
ここで布団敷いて反物たちの横で添い寝したいほどです。
—
日本ブログ村に参加しています。
ぽちっと投票お願いします。
令和七年一月二十九日
随筆家、ライターの友人に会いました。
昨年の五月以来の再会。
友人の好みは久留米絣の木綿着物に木綿の袴という旧制高校生、書生風、大正ロマン風といった姿ですが、体格のこともあって着物も袴もご自身の寸法に誂えたもので、普段着としているそうです。
今回は全身写真は撮ってないので伝わりにくいですが、日常着にしている事がよく分かるほど馴染んでいて、一時的な着物感やコスプレ感は無く「日本人が全員着物で生活していた頃の人」といった雰囲気です。
お会いした場所は東京都東久留米市、東久留米駅に近い『イーストエンドホワイト珈琲』で、たまに行くお店で雰囲気が隠れ家的で好み。
小型電子記録写真機しか持っていかなかったのですが「後ろ姿の美学」的な写真を撮影しました。
↓下は私です。
日本ブログ村に参加しています。
ぽちっと投票お願いします。