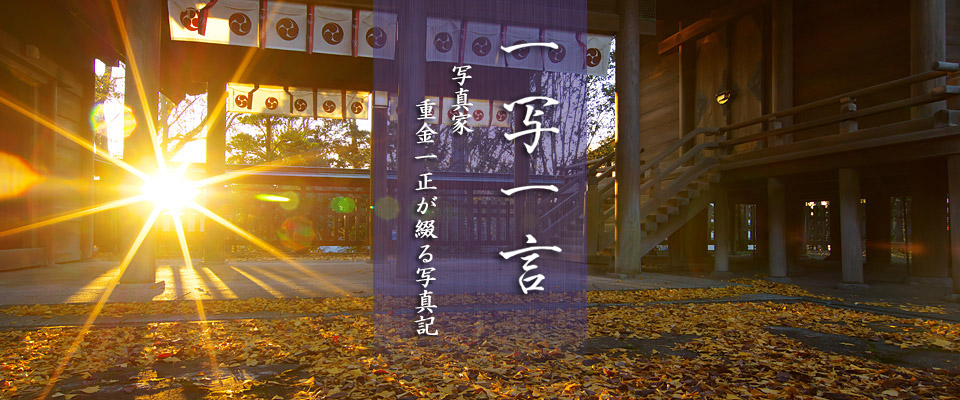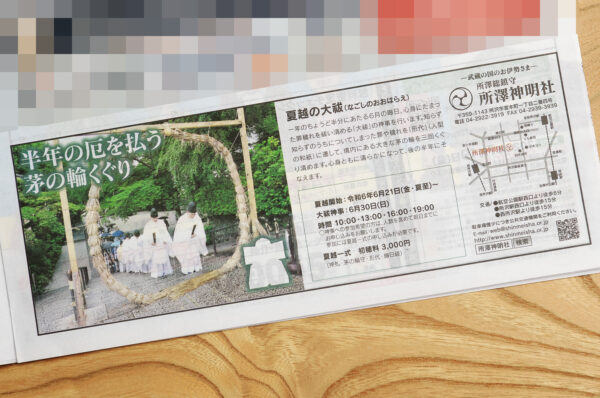下駄の底ゴムのお話。
下駄には接地面にゴムを貼っています。
膝の手術後、古傷の関係で膝への負担からしばらく下駄を避けていました。
しかし、やはり雨の日に下駄は必要不可欠ということで、膝の負担を和らげるために緩衝材として「近藤」の底ゴムを貼って使っています。
理学療法士さんから平衡良く歩くように言われていることもあります。
ゴムの山が無くなると、剥がして(やすりで削り取る)張り替えます。
自分の膝に対する緩衝のほか…
下駄歯に小石が食い込まないので、写真展の会場や美術館には床を気にせず入りやすくなります。
近藤の底ゴムは色が下駄に似ているので目立たないのと、薄いので歩き方で多少はカランコロン音を立てる事ができます。
木目でわかると思いますが、台と歯が一体で削り出された連歯下駄なので大事に履いてます。
ちなみに下駄専用の三平ゴムは厚みがあり過ぎて、つま先が地面に当たるくらい前に傾くと角度が強くて危ないし、下駄らしい音が全くしないので❌️。
三平ゴムはすり減った下駄に貼るには良いかもしれません。
日本ブログ村に参加しています。
ぽちっと投票お願いします。