八月初旬に購入しておいた本麻の足袋です。
届いてから一ヶ月以上経って、やっと開封しました。
徳島の「美津菱足袋株式会社」さんの本麻足袋。
表生地、裏生地とも薄手で涼しそう。
生地の肌触りはスルッとしていて柔らかです。
紺の色も好みの色。
思っていた以上に良さそうです。
実際の履き心地はまた今度。
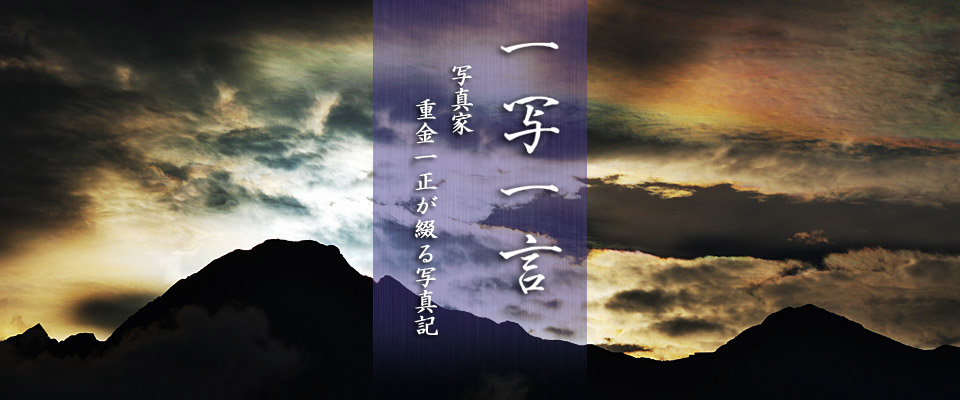
八月初旬に購入しておいた本麻の足袋です。
届いてから一ヶ月以上経って、やっと開封しました。
徳島の「美津菱足袋株式会社」さんの本麻足袋。
表生地、裏生地とも薄手で涼しそう。
生地の肌触りはスルッとしていて柔らかです。
紺の色も好みの色。
思っていた以上に良さそうです。
実際の履き心地はまた今度。
久しぶりに神楽坂(東京都新宿区)へ行ってきました。
神楽坂はコロナ禍以前に戻ったのではないかと思うような人通り。
車両通行止め歩行者天国でした。
—–
神楽坂毘沙門天 善國寺で行われた「紺屋めぐり・染の王国新宿 染職人の感謝祭」
江戸小紋、江戸更紗、東京手描友禅、その他染め物など各工房それぞれ。
—–
反物買ってないのに、手ぬぐいをいただきました。
買い置きしておいた浴衣の反物を和裁士さんに仕立てていただきました。
いかにも古典的な枡の柄の浴衣なのですが、ばつ✕な模様が追加されたような意匠です。
ふらっとそのへん用・・・です。
この浴衣の反物の製販元は古典的な柄を元に手を加えたような意匠が多く好みの意匠が結構あるんです。
在庫限りのようですが、このシリーズもう一本くらいあってもよいな~
袖を通してみました。
浴衣なので角帯の結びを貝の口にしようとしたら、ん~~納得いかず。
貝の口って、年単位で結んでないかも。。。
というわけで片ばさみにしてみましたが、あまり使ったことがない角帯でいまいち締まりが悪い。
こういう浴衣に合う角帯って、返って難しい
「佐藤洋宜 東京手描友禅展」へ行ってきました。
場所は 西東京市西武柳沢駅から徒歩一分 ギャラリー Space-KOH
しゃれ帯展の時にかわいいなぁ~と思っていた雀の帯を見ることができました。
雀を描く作家さんの印象です😁
雀のほかに、フクロウやカワセミ、うさぎも描かれていました。
猫の振り袖は、お話が楽しいです。必見&必聴❗
すべて女性ものですので、購入対象としてみているわけではないですが、意匠、構図、色、また作品に至るまでのお話を聞くのは写真を撮るうえでも参考になる部分が多く勉強になり楽しいです。
帯にコディネートされていた着尺は、どれも破格な価格でびっくり。
縞大島とか本麻の小千谷とか、早いものがちかもね~。
埼玉県所沢市 北野天神社 奉納『夜桜あかり』
夜桜あかり実行委員会の委員として企画、照明の監修、設営準備、開催中の案内などを行っています。
令和三年の桜は開花が早く、桜への夜間照明は三月二十二日から四月八日まで行いました。
北野天神社の『夜桜あかり』は、氏子崇敬者有志による奉納として平成三十一年に桜の開花から始まりました。
境内に堂々と四方八方に枝を伸ばす樹齢70年超のソメイヨシノは神社の景観と相まって優雅です。
「夜桜あかりは」この現在の優雅な姿を多くの方に見て頂きたい、知っていただきたい、残していただきたい、との想いで企画しています。
また、次の春に一本の桜の木の下に人々と神様と笑顔で集まれますよう。
観光地ではないため人出は密になるほどではありませんが、感染症対策として消毒スプレーは手水舎に設置、必ずマスク着用、対人距離の確保をお願いしました。
夜桜あかりの期間中、三月二十七日と四月三日の土曜日は和服でおりました。
小さい写真機で撮影して頂きましたが、画質が厳しいです(^^;)
昨年の仕事ですが、長野県上田市のインバウンド向け観光パンフの表紙に写真を使っていただきました。
写真は上田紬の小岩井紬工房さんのりんご染めの反物です。
小岩井さんのりんご染めはとても美しく、美味しそうな色で、絹の光沢や光の加減と相まって表現される美しさには見ているだけでうっとり。心が落ち着きます。
今回のパンフを手にした瞬間、正直、印刷の色の悪さには驚きましたが、この手の印刷物の発色は致し方ないところです。
令和二年八月二十二日
東京都、新宿区落合(最寄駅・中井)の染元、二葉苑さんへ。
たまに遊びに立ち寄るお気に入りの染元さんですが、今回は「浴衣でインスタ写真&小さな花火大会」として反物の外展示。
反物で撮影スポット作ったとのことでふらりと・・・
—
藍のお茶
藍のお茶です。
クセのあまり強くない爽やかなハーブティと言った感じで、好きなお味でした。
—
綿麻を浴衣な感じに。写真を撮っていただきました。
男着物の方がもう一人来られて。
夕方、良い風が窓から入って、すっかりくつろいでしまいました。
楽しかったなぁ~
9月は5日、6日、12日、13日も行うそうです。
少し涼しくなって気持ち良いかも。
また行きます。
私の着物の整理の仕方。
比較的着るもの、着る可能性のあるものは、たとうしの手前を着物の下に折り込んで色柄が見えるようにしています。
手前の紐を結んでも良いのですが、結ばずにクローゼットの棚に収納しています。
こうして色柄が横から見えるようにしておくと、わかりやすいのです。
直しが必要な物や、明らかに年単位で着ないもの、着られないものは、桐の着物用の衣装箱へ収納しています。
桐の箪笥は持っていません(欲しいけど…)
令和二年三月五日
新宿プリンスホテルで行われていた二葉苑さんの染色体験。
会場は、なんとホテル内のパーティースペース・ガーネット。
素敵な回廊をくぐり、扉の先では反物がお出迎え。
なんという素敵な空間、お洒落すぎる😆
会場の雰囲気と展示されていた着物の共演も見事でした。
二葉苑さんの公式で発信されていた内容から、これは間違いなく見ておくべき!と確信。私は染の体験は行っていないのですが、仕事の帰りに立ち寄って見学、撮影させていただきました。