令和七年十月十八日、男の着物仲間、友人と所沢市の所沢航空記念公園で会いました。
航空公園内の茶店『彩翔亭』でお抹茶を一服。
見ての通り日常着すぎるほどの普段着着物な方向性で共通点が多い友人です。
着物の話がほとんどですが、そのほか共通の話題も多く時間経つのがあっという間でした。
日本ブログ村に参加しています。
ぽちっと投票お願いします。
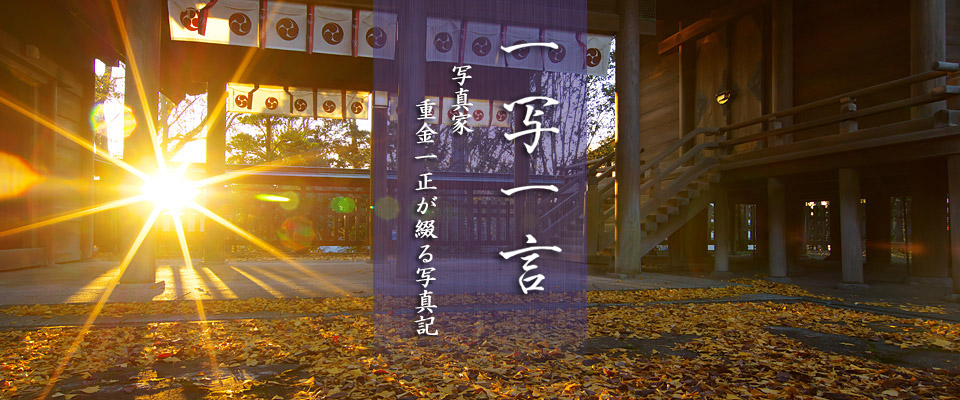
鬢付け油を自作する場合、木蝋と白蝋、どちらが使いやすのか。
『木蝋』はハゼノキの果皮から圧搾して得られる油脂で生蝋とも呼ばれます。
『白蝋』は木蝋から精製して不純物が取り除かれ、漂白したもの。
白蝋を使って鬢付け油を作ってみたのですが、今までの木蝋を主原料とした鬢付け油に比べ、同じ配合比率にしてもかなり硬いです。
融点は木蝋が52.6度、白蝋が52.4度でほぼ同じですが、白蝋はニ塩基酸が含まれていないため、木蝋のような粘り強さは無いとのこと。
白蝋で鬢付け油として扱いやすい硬さにするにはひまし油の割合を少し増やす方法ですが、鬢付け油としての融点が下がってしまいます。
鬢付け油としての融点が下がると、気温の高い時期は溶けて髪型が崩れやすくなります。(私の場合だとおくれ毛が落ちやすくなり刷毛先が崩れやすくなる)
ベタツキ感がなくサラッとしているので硬さを利用して髷の刷毛先に使うのは良さそうです。
ただし、刷毛先を整える時にコテを使う場合に限られそうです。
というわけで、ひまし油で硬さを調整することを前提とした場合、鬢付け油として使うのであれば『木蝋』を原料とするほうが扱いやすいようです。
日本ブログ村に参加しています。
ぽちっと投票お願いします。
入間市文化創造アトリエ『アミーゴ』(旧埼玉県繊維工業試験場・仏子模範工場)で行われていた川越唐桟の展示を見に友人と行ってきました。
機械織りは何度も見たことがあったのですが、手織りはあまり見たことがなかったかも。
ふわっと柔らかい感触で反巾一尺一寸は現代人には魅力的です。
木綿とはいえ普段の活動着に(写真機鞄や三脚を担ぐなど)するにはもったいないほどの風合いと…価格😅でした。
今回、川越唐桟と同時に関心があったのは、会場となっている『入間市文化創造アトリエ『アミーゴ』(旧埼玉県繊維工業試験場・仏子模範工場)』です。
大正五年に建築された建物でその雰囲気は気になるところ。
–
写真二
大正ロマン風な友人N氏

同行した友人は普段着として大正ロマン風な和装姿を好んでおり喜んでおりました。
–
–
写真四
赤いノコギリ屋根の館内では声楽の催しが行われていました。
庭も良い雰囲気🌿

–
写真五
私。
館内のカフェにて。入間産の紅茶(和紅茶)、美味しかった~☕

日本ブログ村に参加しています。
ぽちっと投票お願いします。
川越の『和紙の山田』さんで、白い水引、100本束を購入してきました。
髷を結う時の元結紐として、以前、十本購入して試していたのですが、長さが90cmあり、好みの白さと太さで、締める時の力加減もわかってきて気に入ってしまいました。
※お店の方に撮影していただきました。店内での撮影許可、投稿許諾済みです。
この写真の時は白い水引で結っています。
古典的な気分?のときは飯田の鬼引き元結、雨の日など濡れる可能性がある場合は麻こより、、、と、使い分けようと思います。
写真に写ってるように、色に種類があるんですよね。
金とか銀とかキラキラしたのを使ったらマツ◯ンさんもびっくり???かと思って確認したらマ◯ケンさんは遥かその上✨️をいってました😂
水引の束の整然とした流れを見たら撮りたくなってしまい…
単純な配光ですが撮っておきました。
日本ブログ村に参加しています。
ぽちっと投票お願いします。
常に二つ折りの髷(諸大夫風)を結っていると思われている方がいるようですが、そうではありません。
通常は「茶筅総髪」、現代的に言うと「ポニーテール」にしています。
髪が着物に付くと着物が汚れやすくなりますので、髪を下ろしたままにしておくことはありません。
「茶筅総髪」は、江馬務著『日本結髪全史』、金沢康隆著『江戸結髪全史』といった著書には江戸時代までは男の髪型として紹介されていますが、同様の髪型で女性の髪型としての紹介はありません。
—
二つ折りの髷(諸大夫風)は自分で20分程度で結えますので、結いたい時に結っています。
日本ブログ村に参加しています。
ぽちっと投票お願いします。
令和七年三月二十九日
武州川越の一番街で行われていた「江戸の日」、地毛髷の結髪実演、どんな雰囲気で行われているのか、見ておきたいと思いまして。ちょいと行ってきました。
見物者は三十人程度かと思いますが傘をさしての立ち見では それ以上の見物人数は難しいでしょう。
雨の中としては盛況だったのではないかと思います。
手伝っている写真館で 成人式の撮影時に日本髪風な方を撮影することがありますが、”日本髪風”ではなく本職の結髪師さんが本格的な日本髪を結うと その仕上がりと美しさに圧倒されます。
女性の髷は華やかで良いです。
が、写真を撮ることを忘れました(^_^;)
—
川越ですので私も髷を結っていきました。
見物者の中にSNSで相互フォローになっている「未告」さんがおられまして、私の写真を撮ってくださいました。
ありがとうございます。
私自身は一枚も写真を撮ってなかったので、撮っていただいた写真の中からの投稿です。(少し画像処理しています)
髷尻を後ろから見た時の🍙おにぎり型、私のこだわり部分です😊
日本ブログ村に参加しています。
ぽちっと投票お願いします。